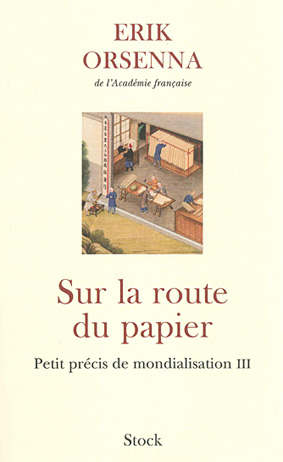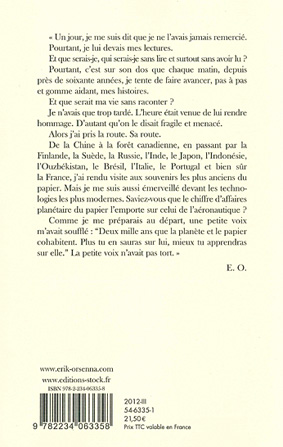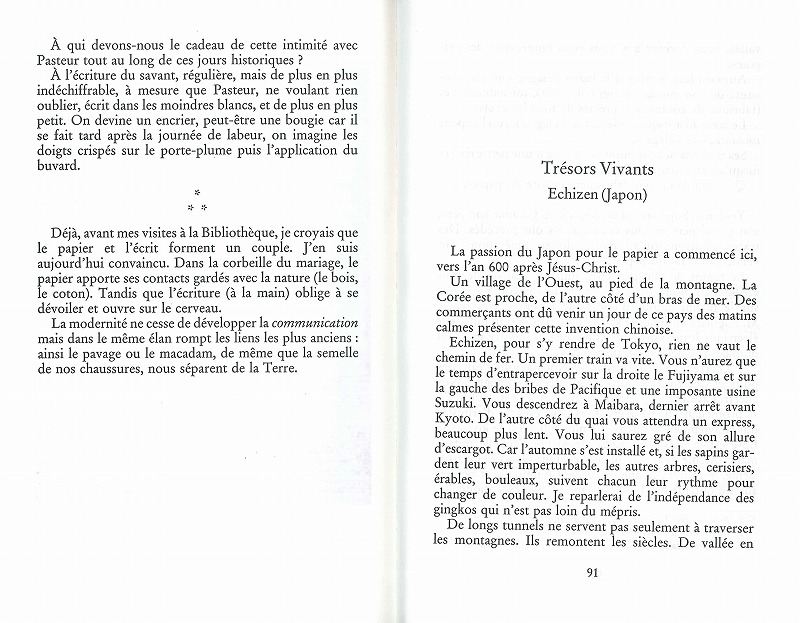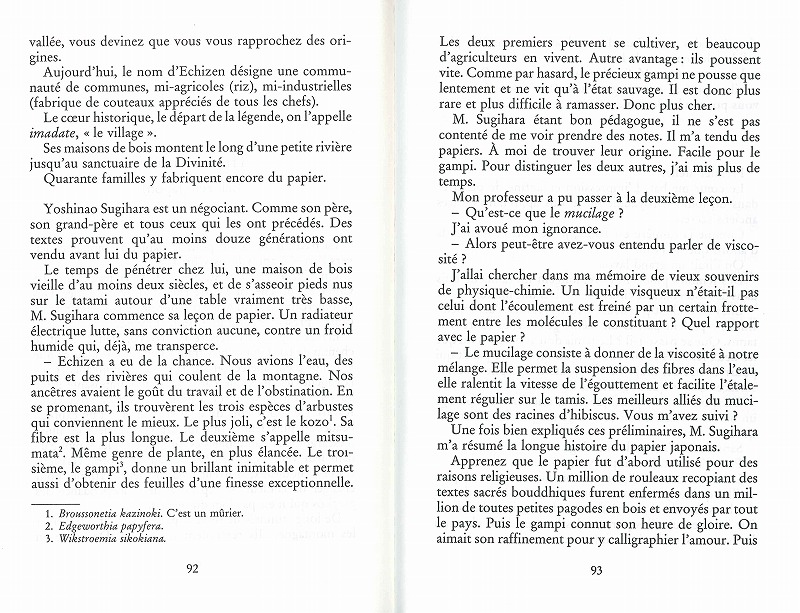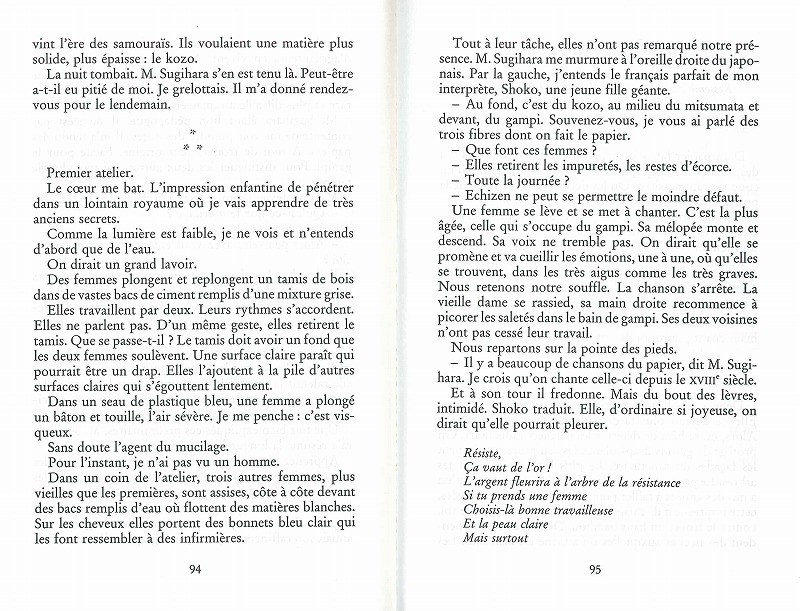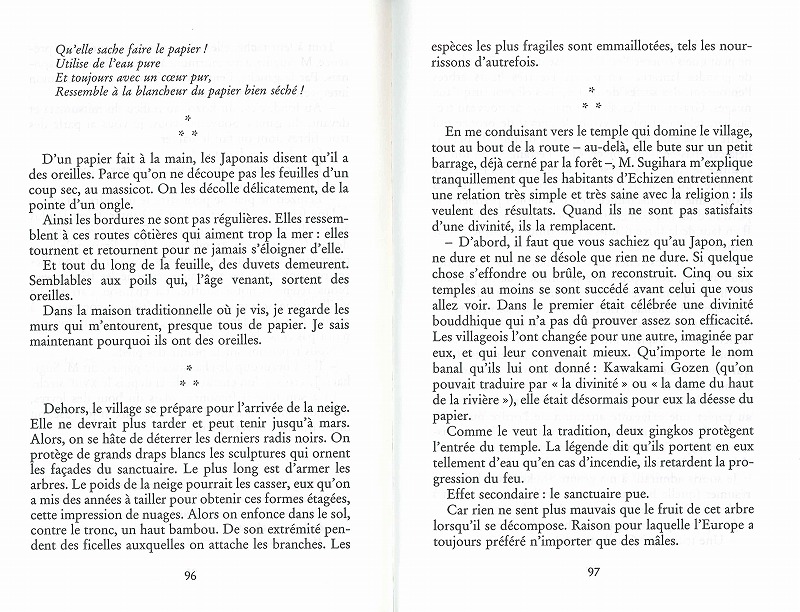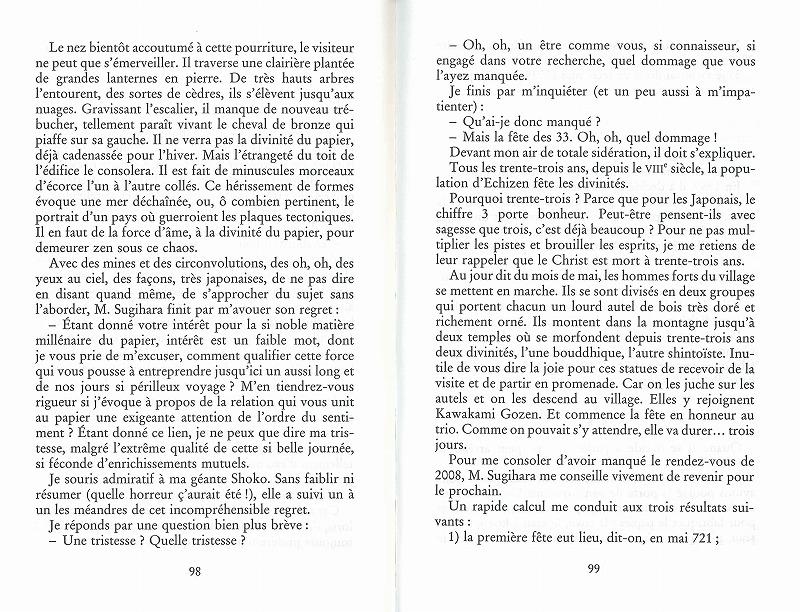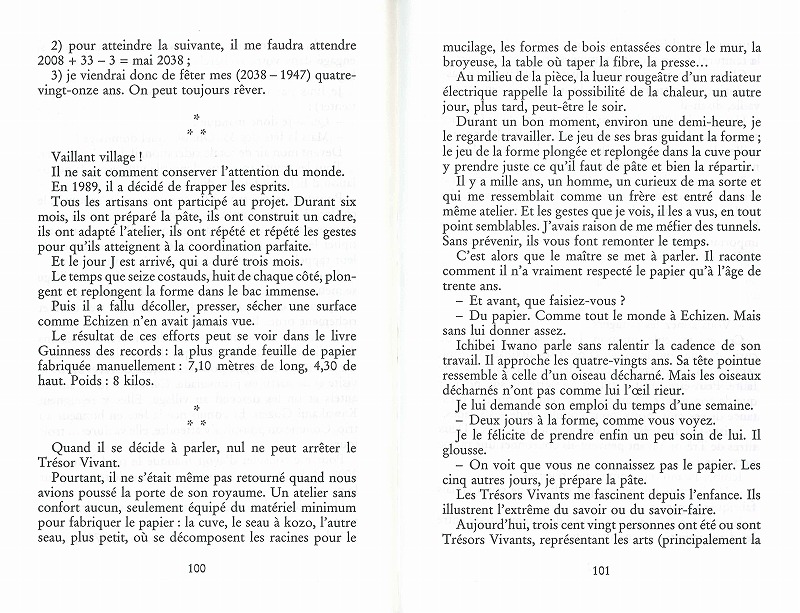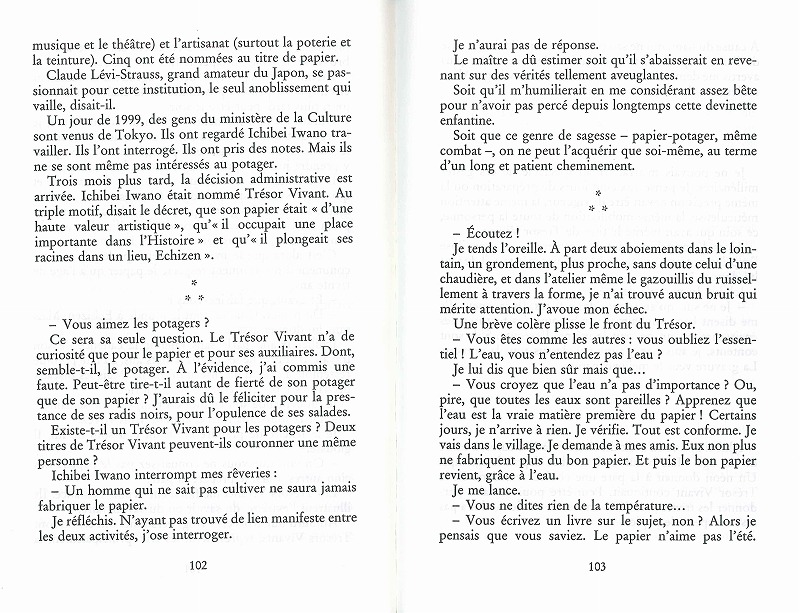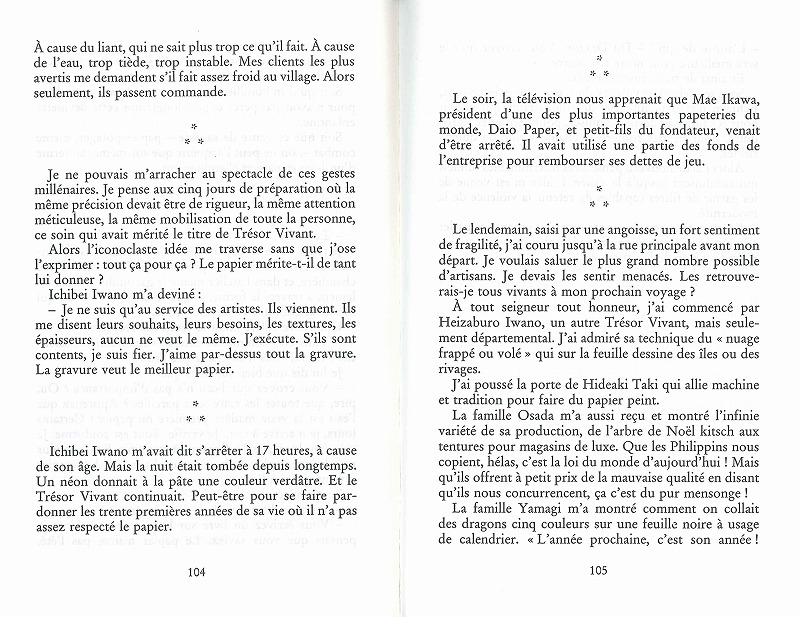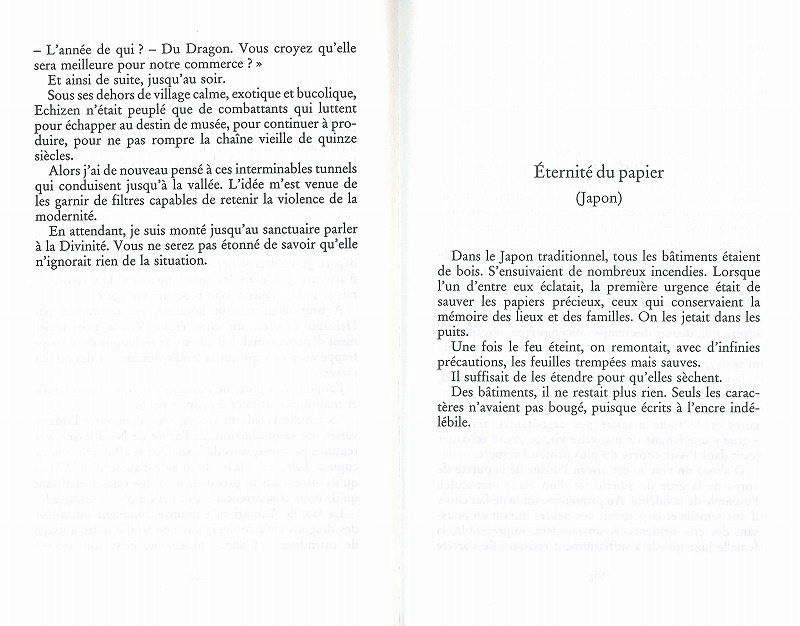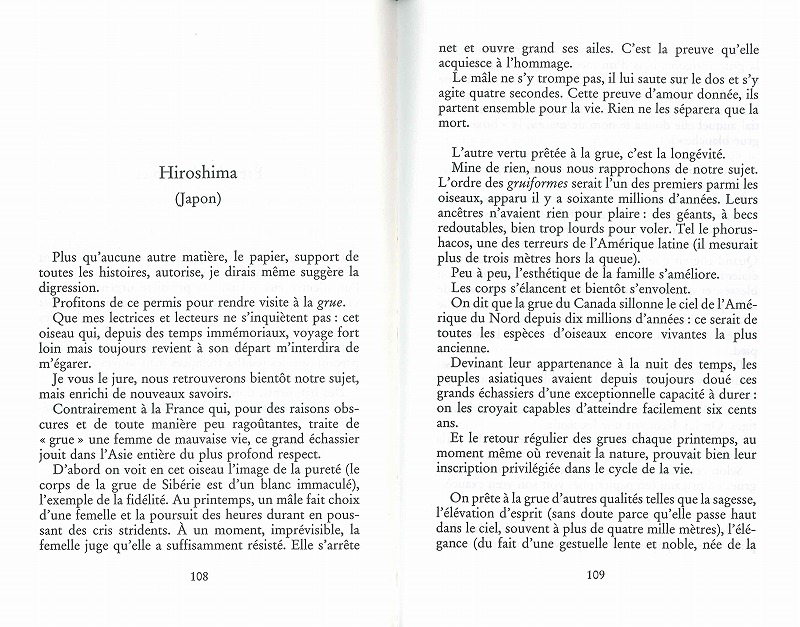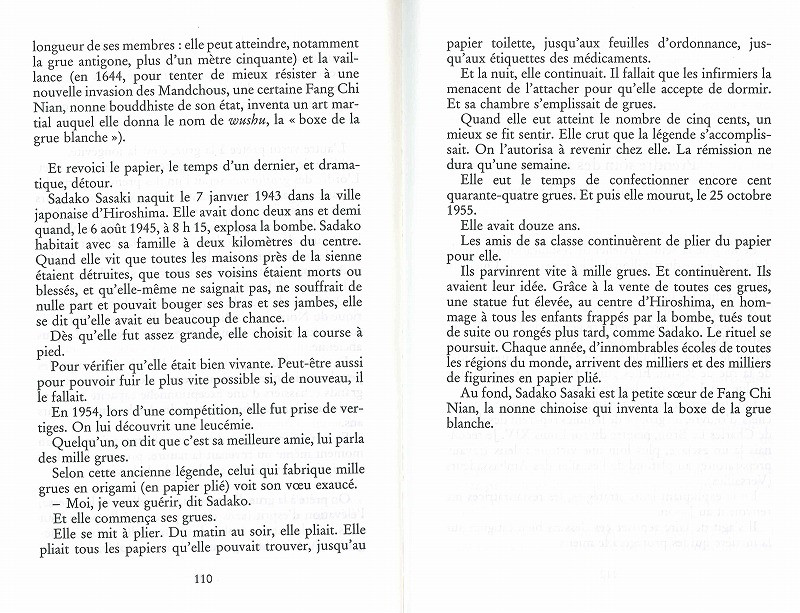ここで、日本の紙に対する情熱は、だいたい西暦600年ほどに始まった。
ある西の、山のふもとの町。海のかいなの逆側の端には、韓国が近い。静かな朝が何度も繰り返されたその土地に、ある日、商人たちがこの中国の発明品を手にして現れたに違いない。
越前、東京からその土地を訪ねるなら、鉄道に若(し)くはない。新幹線は早い。左手に富士山を、右手に太平洋のかけらや、スズキの堂々とした工場を垣間眺める数時間しかかからない。京都の手前の停車駅、米原で降りる。プラットフォームの別の乗り場で、別の電車を捕まえる。今度はずいぶん遅い 。そのカタツムリのような歩みが気に入るかもしれない。なぜなら、秋が着ているのだし、もしモミの木がその常緑葉を残していれば、桜桃、カエデ、樺の木といった他の木々が、それぞれのリズムで引き続き、色を変えてゆくのが眺められるからだ。ほとんど馬鹿にされている銀杏の木の独自性についてはやがてまた語ろう。
長いトンネルは、山をくぐり抜けるためだけの役目を果たしているわけではない。それは、幾つもの世紀を遡っていくのだ。谷の中の谷、起源へと自分が近づいていくことがわかる。
こんにち、越前という名前は、複数のコミューンの共同体を示す。半ば農業的(米)で、半ば産業的(あらゆる料理人に高く評価されている包丁の製作所)なものだ。
歴史的な心、伝説に発して、今立群は、「その村」と呼ばれている。
そこの木造家屋群は、小さな川をずっと遡ってゆき、聖域へと達する。
そこで、5つの家族が、今も紙を作っている。
スギハラヨシナオ氏は卸売り商である。彼の父、祖父、そしてその前5代に渡ってと同じく。資料は、彼以前の6代にわたって紙を売っていたということを明らかにしている。
時間が彼の家に染み込んでいる、少なくとも2世紀は古い木造家屋、そして畳の上で、本当にとても低い机の周りに裸足で座って、スギハラ氏は紙に関する授業を始める。電気暖房が、まったく自信無さげに、すでに私をさいなむ湿った寒気と戦っている。
「越前は運を持っていました。我々には水があり、井戸と、山を流れる川がありました。我々の先祖は勤勉と粘り強さへの好みを持っていました。歩き回っていて、彼らはもっとも適した3種類の小低木を見つけます。一番よいのはコウゾでした。その繊維は一番長いのです。2番めは、ミツマタです。同種の植物で、加えてすらっとしています。3番めのガンピは、すばらしく類比のないものを提供してくれ、例外的なきめ細やかさを持った葉を手に入れさせてくれます。前者の2つは栽培可能で、多くの農家がその栽培を営んでいます。そのほかにも利点として、それらは芽を出すのが早いです。まるで偶然であるかのように、精巧なガンピはゆっくりとしか芽を出さず、野生の状態でしか育ちません。そういうわけで、ガンピはより集めるのが難しく、より珍しく、だからこそより高価です」
スギハラ氏はよい教師だった。彼は私がノートをとっているのを見るだけでは満足せず、私がその材料を発見できるようにと、幾枚かの紙を差し出した。ガンピに関しては簡単だった。他の2つを見分けるために、私はより多くの時間を注いだ。
私の教授は2つ目の授業へと進む準備ができたようだった。
「粘質液とはなにかわかりますか?」
私は自分の無知を告白した。
「それでは、ひょっとして粘度に関する話なら聞いたことはありませんか?」
私は、記憶の中から、古い物理化学の思い出をかき集めようとした。ネバネバした液体というのは、それを構成している分子間のある種の摩擦によって動きを阻まれた流れのようなものだったのではなかったか? それと紙との関係とはなんなのだろう?
「粘質液は、我々の合成物に粘度を与えるための構成物となります。そのおかげで、水に入れられた繊維が浮遊するようになり、水切りの速度がゆるまり、畳の上に綺麗に広げることが容易になります。粘液を持った最もよい盟友は、ハイビスカスの根っこになります。ここまでついてこれていますか?」
一度こうした前置きを見事に語ってみせて、スギハラ氏は私に日本の紙に関する長い歴史の要約をしてくれた。
第一に、まず紙は宗教的な理由によって使用された。仏教の経典を書き写した無数の巻物が、無数の小さな木造寺院に所蔵され、また国中に移送されなくてはならなかったのだ。次に、雁皮紙がその栄光の時を迎える。人々は、その上に愛の言葉を飾り書きするために雁皮紙の洗練を愛した。それから、侍たちの時代が来る。彼らはよりしっかりして、より厚い素材を好んだ。つまり楮紙である。
夜が来た。スギハラ氏は、そこで姿勢を保っていた。おそらく寒さに震える私に哀れみを感じたのだろうか、彼は翌日の会合の約束をしてくれた。
***
第一の工房。
その精神性が私の胸を打つ。そこでとても古い秘密ことになる遠い王国へと入っていくのだというような、子供っぽい印象を持つ。
幽かな光のため、私は最初、水を見る、あるいは水を聴くことしかできなかった。
ここは大きな共同洗い場だという。
灰色の混合物で満たされた、巨大なセメントでできた桶に、女たちが木製のふるいを繰り返し漬けていた。
彼女たちは二人一組で仕事をしていた。二人のリズムは一致している。彼女たちは口を利かない。同じ動きで、二人はふるいを引き出す。何が行われているのだろう? 二人の女で持ち上げているふるいには、底があるはずである。その漉けた表面は、まるで毛織物のように見える。彼女たちは、それを他の、ゆっくりと水を滴り落としている透けた表面たちの上に重ねる。
青いブラスチックのバケツの中に、一人の女が棒をつき入れてかき混ぜた。厳しい空気。私は身をかがめた。バケツの中は、ねばねばとしていた。
おそらく粘質液の担当者であろう。
今のところ、男の姿は見ていない。
工房のすみに、上に触れた女たちと比べて年老いた3人の女たちが、白い物体が浮いた水に満たされた桶に向かって、隣合わせで座っている。髪の上に青い透けたボネットをかぶっていて、それが彼女らを看護師のように見せている。
仕事に没頭しきっていて、彼女らは私たちの存在に気が付かないでいる。スギハラ氏は私の右耳に日本語で何かを囁く。左側で、私の通訳、体の大きな若い、ショウコという女の子が、完璧なフランス語を喋るのを聴く。
「底にコウゾがあり、真ん中にミツマタがあり、そして手前にガンピがあります。覚えていますか、あなたに話した、そこから紙を作る3つの素材です」
「彼女たちは何をしているのでしょう?」
「不純物、樹皮が残っているのを引き出しているのです」
「一日中ですか?」
「越前はほんの些細な欠陥も許さないのです」
一人の女が立ち上がり、歌い始める。ガンピを担当している、一番年老いた女だ。その単調な旋律が、上がり、また下がる。彼女の声は震えてはいない。彼女は歩きまわり、感情をひとつずつ詰み集め、より鋭く、より厳粛な状態になるのだという。私たちは息をひそめる。歌が止む。老女は再び腰を下ろし、右手でガンピの浴槽から塵をついばみはじめる。他の二人はその間も手を止めてはいなかった。
私たちはつま先立ちで立ち去る。
「紙にかんする歌はたくさんあります」とスギハラ氏は言う。「これなどは18世紀から歌われているものだとおもいます。」
そうして、今度は自分の番だというように彼は口ずさむ。しかし、唇の先でおどおどと。ショウコが翻訳する。いつもは陽気な彼女だが、ほとんど泣きそうだったということだ。
耐えるんだ
これは金の価値がある!
忍耐の木から銀が花咲く
もしもお前が嫁とって
働き者の嫁を
明るい肌の嫁を
でもなにより
紙作りを知ってる嫁を選ぶなら!
使うのは真水
そしていつも真心で
乾いた紙ほど真っ白な心で!
***
手に慣れた紙に関して、日本人は紙に耳があるという。彼らは裁断機のきつい一撃で紙を切り刻むのではない。爪の先で、やさしくはがすのだ。
そうすると、紙のふちは一定の形にはならない。海のことを強く愛する海岸の道路、海からけして遠ざからないよう、曲がってはまた曲がる道に似たものになる。
そして紙に沿って和毛が残る。歳を重ねたときに、耳から出てくる毛に似た。
私が滞在した伝統家屋で、私を取り囲んでいる壁紙、ほとんどどこも紙でできたものを私は見る。今、私はなぜ紙に耳があるというのかわかる。
***
外では、村が雪の到来に備えている。雪はもうそうもたもたもしていないだろうし、3月まで残るのだ。だから、人々は急いで最後の黒大根を掘り出す。聖域のファサードを飾る彫像に、大きな白い布を巻きつけて保護する。一番長くかかる作業は、木に防護を備え付けることだ。雪の重さで木が潰れてしまうかもしれないのだ。木は長年の作業によって、段々状に伐りそろえられている。人々は地面に長い竹の棒を打ち込み、幹を支える。竹の棒の先からは紐が出ていて、枝がくくりつけられる。もっとも脆い種類の木々は、それが育て上げられたときのように、すっぽりくるまれる。
***
道をずっと言った先、村を見下ろす神社にスギハラ氏は私を連れてゆく。神社は堰にもたれかかるようにして、もうほとんど森に囲まれている。その道中、スギハラ氏は、越前での、信仰に対するとてもシンプルでとても健やかな関係を、静かに説明する。ここでは人々は結果を求める。神に満足が行かなければ、それを取り替えてやる。
「まず、日本では何もずっと不変であるということはなく、また、誰もなにかが不変でないということを嘆き悲しんだりしないということを知っておかなくてはなりません。もし何かが崩壊したり燃えたりしたなら、建設し直します。少なくとも5つか6つほどの神社が、もうすぐ見ることになる神社の前に継がれています。最初の寺院では、仏教の仏が祀られていましたが、その効果がじゅうぶんに示されることがありませんでした。村人たちはそれを、自分たちで考えた別の神と取り替えて、こんどはうまくいきました。面白いことに、彼らはその神にずいぶんありきたりの名前を与えました。「カワカミゴゼン」というのですが、これは「神」を翻訳したような名前かもしれず、「川の上流にいる婦人」というようなものかもしれません。それ以降、彼女は村人にとって、紙の女神でもあります」
伝統の要請によって、2本の銀杏の木が、神社の入り口を守護することになる。伝説によれば、それらの銀杏はまた、そのうちに水を宿していて、火事の際にはそれによって火の広がりを抑えるのだという。
第二の副次的な効果、神社は臭う。
その木が成す実が腐っていくときほど、嫌な匂いがするものはない。そういったわけでヨーロッパは雄の木だけを国に持ち込むことを好んだのだ。
時期に鼻がその腐敗臭になれることには、訪問者はただ驚くばかりだ。石灯が立ち並ぶ広場を横切ってゆく。スギ類の木々の高さと言ったら、ほとんど雲に届かんばかりだ。階段を登ってゆく訪問者は、またあやうくよろめきそうになるが、同じように、ブロンズでできた馬がその左足を高く上げている。すでに冬に閉じ込められて、その像は紙の神のようにはみえない。しかし、建造物の屋根の奇妙さがその印象をやわらげる。屋根は、樹皮のようなごく小さい断片が互いに貼り合わされることでできている。その形態の毛羽立ったような立ち並びかたを見ていると、猛り狂った海、あるいは、ああなんと適切なたとえだろうか、地層が争い合う大地のポートレイトのような印象がかきたてられる。紙の神のもとで、その沸き立つカオスの下にあって禅の心を保ち続けるのは、ずいぶんな魂の強さを必要とする。
いくつもの顔つきと旋回、おお、おお、という声に、目は天に向けて、言うと同時に言わない、また話の主題に近づくことなく身を寄せる、という日本的なやり方で、スギハラ氏はついに私に彼の無念を打ち明ける。
「千年来の高貴な物質、紙に対するあなたの興味を考えると、興味などという言葉では生ぬるいですね。だって、許して下さい、あなたにこの冒険、はるばるこんな遠いところまで時間をかけてやってくるこの冒険を試みる気にさせた力を、どう測ればいいのでしょう? ちょうどあなたを紙と結び付けられている関係の、感情の秩序のうちの貪欲な注意力のことを思い起こすと、あなたが私に厳しい評価を下すのではないかとおもいます。その絆のことを思うと、私はただ自分の悲嘆を打ち明けることしかできません。たとえ、この一日がどれほど美しく、私たちが互いを潤す関係がどれほど実り豊かなものであったかというと、まさにその最高程度の状態であったにもかかわらず」
私はわが巨人娘のショウコに感嘆を示して微笑む。弱めたり、簡潔にまとめたりすることなく(もしそうされていたらと思うと身の毛がよだつ!)、彼女は一歩一歩、ほとんど理解不能な無念を語る曲がり道を、辿りきってくれたのだ。
私はそれに比べてはるかに粗野な質問で返した。
「悲嘆? どんな悲嘆ですか?」
「おお、おお、これほど目利きで、これほど探求に熱心なあなたのような存在が、あれを逃してしまうなんてなんてひどい損害でしょう」
私はついに不安になり(そして少し辛抱がたまらなくなり)、訊ねる。
「それで、私は何を逃してしまったのでしょう?」
「33年毎のお祭りです。ああ、ああ、なんてひどいことでしょう!」
私がすっかりショックを受けている姿に面して、彼は説明の必要を感じたようだ。
33年毎に、18世紀以来、越前の人々は神様を祝ってきた。
どうして33なのだろうか? それは、日本人にとって、3という数字は幸運を担っているからである。追跡のための足あとをむやみに増やさないように、また精神をかき乱してしまわないように、私はキリストもまた33歳で死んだということは考えないように務める。
5月のある決まった日に、村の力強い男たちは集まって行進をする。彼らは2つのグループに別れ、それぞれが金メッキされ、豪華に飾り付けられた木製の重いみこしを担ぐ。彼らは山を登って行って、やがて2つの神社にたどり着くのだが、その神社では33年間ずっと、2つの神、片方は仏教の、もう片方は神道の神が、彼らを待ちあぐねている。訪問者を迎え、そして彼らの歩みとともにそこを出発する彫像の喜びに関しては言うまでもないだろう。なにしろ男たちはみこしにそれらの彫像を載せ、そして街まで下っていくのだ。そこで彫像たちはカワカミゴゼンと合流する。そうして、3つ一組の彼らに敬意を表して祭りが始まるのだ。それに参加している人々と同じく、神たちは3日間の祭りにとどまる。
今が2008年で、私がそれを逃してしまったことを慰めようと、スギハラ氏は生き生きとした調子で、次の祭りの来るように助言をくれる。
速やかな計算によって私は以下の3つの結論に導かれる。
1):最初の祭りは、721年の5月に行われたという。
2)次の祭りに参加するためには、私は、2008+33−3=2038年の5月にやってこなくてはならない。
3)したがって、(2038−1947)で祭りに参加する私は91歳になっているだろう。…がまあ夢をみる資格はいつもだれにでもあるのだ。
***
雄々しい村!
世界からの注意をどのようにして保つのか、その村はかつて知らなかった。
1989年、村は人々の精神を撃つことを決めた。
すべての職人がその計画に参加した。6ヶ月の間、彼らは記事を準備し、枠を組み立て、工房を適応させ、何度も何度もきまった所作を繰り返し、やがて共同作業が完璧に達した。
私が着いた日、それは3ヶ月続いているところだった。
それぞれの辺に8人の屈強な男が寄り、広大な桶の中に型を漬けては揚げ、漬けては上げというのを繰り返していた。
それから、越前も未だかつて見たことがないその面を、剥がし、伸し、干さねばならなかった。
その努力の結果は、おそらくギネス記録の本で見ることができるだろう。最も巨大な、手仕事で作られた紙の一葉。長さ7.10メートル、高さは4.30メートル。重さ、8キロ。
***
彼が一度しゃべると決めたなら、何も「生きた宝」に割り込むことはできない。
とはいえ、彼の王国の扉を私達が押したとき、彼は振り返りもしなかった。まったく居心地といったものを欠いた工房。紙を作るための最小限の小道具を備え付けているのみである。桶、コウゾを入れる手桶、より小さい手桶では粘質物のために根っこの分解が進められ、壁に寄せて積み上げられた木の塊、砕き機、そこで繊維をなめしたり、伸したりするためのテーブル…。
一揃いの中に、赤みがかった微光が、電気暖房器から発して、熱の可能性、違う日、または違う夕からでもいい、熱の可能性を呼び集めようとしている。
そのすばらしい瞬間、だいたい半時間ほどだろうか、私は彼が仕事をするのを眺める。彼の両腕が型を導いてゆく喜び、桶の中で広げられ、また広げられるある形、そのようにして生地の満足がゆくまで何度もやり直されるのだが、それを見る喜び。
千年も昔、ある男、私と同種の好奇心に満ちた種類の人間、私とほとんど兄弟のように見えるある男が、まったく同じ工房へ入ってゆく。私がここで見る数々の身振りと、彼がここで見る身振りは、あらゆる点においてほとんど同じである。トンネルをくぐるときに感じた用心しなくてはという気もちは正しかったわけだ。予告もなしに、ここでは時間を遡らされてしまう。
その時、巨匠が喋り始める。紙のことを本当に敬い始めたのは、やっと30歳になってのことだ、といったふうに語り始める。
「それではその前は何をなさっていたのですか?」
「紙だね。越前のみんなと同じようにね。でも、十分に身を捧げてはなかった」
岩野市兵衛は、彼の仕事の回転率をゆるめることなく喋る。彼はほとんど80歳だ。彼の尖った顔つきは、やせ細った鳥を思わせるが。しかしやせ細った鳥は、彼のような陽気な目を持っていない。
私は彼に今週の仕事時間の振り分け方を尋ねる。
「2日間は、あなたがいま見ているように、こんなふうだね」
彼がほんのすこしの細心さで仕事をやりとげる域になっていることを私は讃える。かれはくつくつと笑う。
「誰かが見たら、あなたは紙のこと何も知らないのだと思うよ。今日以外に5日間、私は生地を準備しているからね」
「生きた宝」――「人間国宝」たちは、子供時代から私を魅了してきた。彼らは、知恵ないし、才腕における極みを彩る存在なのだ。
今日、320人が人間国宝として指名されている(あるいは、失くなった人を含めて、いた)。芸術(主に音楽や舞台に関わるもの)、それから職人仕事(主に陶器焼き物、染色技術)を代表している。紙に関しては、これまで5人が指名されてきた。
クロード・レヴィ=ストロース、あの偉大な日本愛好家は、この制度に夢中になっていた。彼いわく、唯一の価値ある爵位授与制度だという。
1999年のある日、文化省の職員たちが東京から訪れた。彼らは岩野市兵衛氏が仕事をするところを眺めた。彼に質問をした。いくつものノートを取った。しかし、彼らは菜園に興味を惹かれるというまではしなかった。
3ヶ月ののち、官僚による決定が届いた。岩野市兵衛氏は人間国宝に指定される。3つの理由がその布告には記されていた。まず、彼の紙が「芸術的に高い価値を有する」こと、そして彼が「歴史的に重要な位置を示している」こと、そしてまた、「彼が越前の地において、影響の根をしっかり伸ばしている」こと。
***
「菜園は気に入ったかい?」
質問はそれだけのようだった。彼、人間国宝は紙とその助けになるものにしか興味を持っていない。つまり、どうやら菜園がその助けになるらしい。明らかに、私は間違いを犯した。どうやら、彼は自分の紙と同じく菜園に誇りを抱いているのだということになるのだろうか? 私は菜園の黒大根の堂々とした風格や、サラダの豪奢について褒め称えなくてはならなかったようだ。
菜園に関する人間国宝というのはあるのだろうか? あるいは、人間国宝の称号が2つ、同じ人間にの頭を彩る冠として与えられるということは?
岩野市兵衛氏は私のそんな夢想を遮って言う。
「菜園を耕すすべを知らないやつはね、紙を作り出すすべも知ることはないんだよ」
私はじっと考える。その2つの活動の間にはっきりとした関係を見出すことができずに、私はおずおずと質問をする。
返答はなかった。
巨匠は、何かを見て取ったのだろう。それはあるいは、それほど明白な真実の前ではただ粛々と頭を垂れるしかないということかもしれない。
あるいは、そんな子供でもわかるような謎々をなかなか解き明かすことができない私のことを、無視するにじゅうぶんな愚か者だと測ったということなのかもしれない。
またあるいは、そのような種の叡智、紙―菜園がひとつになってともに争うような種類の叡智には、人は己自身の足で一歩一歩辛抱強く歩く道のりの果てにしかたどり着けないのだ、ということかもしれない。
***
「ほら聴いてごらん!」
私は耳をそばだてる。遠くで聞こえる犬の遠吠えのほかに、もう少し近くではおそらくボイラーのようなものの汽笛が、そして工房のなかでは、仕組みを流れている水の流れのせせらぎが聴こえる。どの音が注意を注ぐべきものなのかわからなかった。私は自分の失敗を告白する。
ちょっとした怒りが、人間国宝の額に皺を生み出す。
「あなたも他の人たちとおなじだね! 大事なことを忘れているのだよ。水だよ、水の音が聴こえないかい?」
おそらくそうだとは思いましたがでも…と私は彼に言いかける。
「水は重要じゃないと思ったということかな? それとも、より悪いことに、水などどれも同じだと思ったのかな? 紙を本当に作っている物質は水なのだと覚えておいておくれ! なかなかの日々をかけて、私はやっとたどり着いたのだよ。私は証しだてできる。すっかり理にかなっているのだよ。村の中でも見ることができる。私は友人に頼んだからね。もういい紙を作ってはいなかった人々だ。そして水のお陰でいい紙が戻ってきたのだ」
私は身を乗り出す。
「あなたは気温に関してはなにもおっしゃいませんね…」
「あなたはこれに関して本を書いているのだろ、違うかい? それだったら知っていると思うのだけれど。紙は夏を嫌う。柔軟性のせいで、それの扱いようがなくなるのだ。温すぎる、ピシっとしない水のせいでね。ちゃんと通暁した私の顧客は、冬に作ってくれるように頼んでくるのさ。だから彼らだけが注文できるわけだ」
***
私はその千年由来の身振りのスペクタクルから自分の身を引き剥がすことができなかった。私は5日間の準備のことを思う。そこでは厳密さの域に達した正確さが、また細心な注意が、また全人格的な没入が稼働されており、それが人間国宝の称号につながったのだろう。
そこで、口にはあえて出さないまでも、聖像破壊的な考えが私をよぎる。このすべてが、紙のために? これほどのものを紙に注いで、紙とはいったいそれに応えてくれるだけのものなのか?
岩野市兵衛氏はそんな私を見抜いた。
「私は芸術家に奉仕する人間にすぎない。彼らがやってくる。彼らが私に言う、彼らの望み、彼らの必要、手触り、厚さ、一つとして同じものはない。私は仕事をこなす。もし彼らが満足すれば、私は誇りに思う。私はね、いつも版画の下に支えになっているのが好きなんだ。版画は最高の紙を必要とするからね」
***
岩野市兵衛氏は私に、17時までじっとして待つように言った。彼の年齢が理由だ。しかし夜の帳はもう随分前から落ちている。蛍光灯が、生地に緑がかった色合いを与えている。そして生きた宝は、仕事を続けている。あるいは、十分に紙を敬っていなかったという人生の最初の30年に関して、自分を許すためなのかもしれない。
***
その晩、我々はテレビで、井川前 氏、世界でも最も重要な製紙会社、大王製紙の会長で、創設者の孫が、逮捕されたことを知った。個人的な遊興費を返済するために、経営権の一部を使用していたのだという。
***
翌日、不安、自分が脆くなってしまったかのような強い感情に身を掴まれ、部屋を出て最初の大きな川まで走っていった。出来る限り大人数の職人に挨拶したいと思っていた。どうやら脅かされるような感覚を持っていたらしい。次の旅では、もっとたくさんの生きた姿を見ることができるだろうか?
あらゆる領主、あらゆる誉れにおいて、私は岩野平三郎氏、また別の人間国宝、ただ県下では唯一のもう一人の職人から始めた。私は彼の技術、「雲華紙」または「雪降紙」に感嘆した。その技術においては紙の上に、島や、川のような文様があらわれるのだ。
私はタキヒデアキ氏の扉を叩いた。氏は模様紙を作るための伝統と機器を持っている。
オサダ家はまた、私を迎え入れ、果てしない種類の制作物を持ってきて見せてくれた。キッチュなクリスマスツリーから、高級雑誌のための壁掛けまで。フィリピン人たちが私たちの模倣をするのだ、ああ、今日ではそれが世界のルールのようなものなのですね! 彼らは私たちと共同で製作していると言って、安い値段で粗悪な品を売るのですよ、まったくの嘘です!とのことだった。
ヤマギ家は、カレンダー用の黒い紙の上に5色の龍をどのように貼り付けて作るのかを見せてくれた。「来年は、彼らの年なのです!」
「誰の年ですって?」
「龍ですよ。辰年です。私たちの商売にはいい年になると思いませんか?」
そしてそうしたように、夜まで私は職人のもとをめぐった。
村の外観、秘教的なところなどなく、静かで牧歌的な風景の下にのみ、越前は美術館に閉じ込められるような運命の流れから逃げ出すように戦う戦士を隠し持っている。そのようにして、5世紀にも渡る古い世界との絆を断たないように、製作を続けているのだ。
いま、またあらたに私は、谷へと続くあの果てしないトンネルのことを考える。この考えは、近代の暴力性の網を抜けてこされるようにして、私のもとにやって来るようだ。
さしあたり、私は神に語りかけるために、聖域まで登っていった。神がそんな状況を知り尽くしていると知っても、あなたは驚かないだろう。
紙の永続性(日本)
日本の伝統において、あらゆる建物は木から作られる。結果として、多くの火事が起こる。その瞬間色々なことがぱっと起こるとはいえ、最も優先される事項は、貴重な紙の束、土地の歴史や家族の歴史を記す紙の束を救い出すことだ。彼らはそれを井戸へと放り込む。
一度火が消えれば、無限の注意を払って、びしょ濡れになってはいるが救われた紙の束を救い上げることになる。
広げてやれば、乾くのには十分だ。
建物に関しては、もうまったく残っていない。文字だけが残る。消えないインクで書かれているのだから。
広島(日本)
他の何よりもまして、紙は歴史の土台として、権威を持つ。が、私はここで脱線をしてみる。
ちょっと鶴に目を向ける許可を頂いて、そこから何かを引き出そうではないか。
読者諸氏は心配する必要はない。太古の昔から、どこまで遠くに行ってもいつもその出発点に戻ってくるあの鳥は、私に脱線を許し続けはしない。
約束するが、じきにわれわれはわれわれが扱ってきた主題を再発見する。ただ今度は新たな知識によってより豊かになって。
「鶴」を、不確かないくつかの理由によって、あまり気乗りのしないやり方で、卑しい生き方をする女として扱うフランスと対照的に、アジアでは、この大きな渉禽類はかなり深い尊敬を受ける役目を担っている。
まず、人はその鳥の中に、たとえば誠実さといった、純粋さのイメージ(シベリアに生息する鶴の体は、まったく純白である)を見る。春になると、雄の鶴は雌を一羽選び、甲高い声を響かせながら、何時間にもわたって彼女を追い続ける。ある予期できない瞬間、雌は自分がもう十分に抵抗したことを知る。彼女は突然止まり、その大きな羽根を広げる。彼女が賛意を受け入れたという徴しだ。
雄は期待を裏切らない。彼は背中に飛び乗って、そこで4秒ほど体を揺さぶり交尾する。そうして愛の証が立てられると、彼らは生涯ずっと共にいる。死の他にはなにも二羽を分かつものはない。
鶴の特性として帰されているもう一つに、その長寿がある。
何食わぬ顔で、我々は話の主題に近づいている。ツル目は鳥類の中で最も古いものの一つ、約6000年前に現れた目である。彼らの祖先は、ぜんぜん愛すべきところを持っていない。巨大な体、恐ろしい嘴、飛ぶには重すぎる体。例えばフォスルラコス などは、南米地域では脅威の一種であった(尻尾を除いても3メートルの大きさがあった。
だんだん、その種の美的な性質が向上してゆく。
体はすらっとしてゆき、飛び立てるようになる。
カナダの鶴は、北米の空を1000万年前から縦横に飛び交っていたという。現在生きている種の中では最も古い種の鳥であろう。
夜になっても鶴の姿ははっきりと見分けることができたため、アジアの人々はずっと昔から、つねにその巨大な渉禽類に、例外的な長続き、長生きという能力を付与して見てきた。鶴はゆうゆうと600歳に達することができると思われていた。
そして、自然が一巡して戻ってくる瞬間だと思われている毎春に、鶴が規則正しく帰ってくることは、鶴が生のサイクルのなかで特権的な地位を持っていることを示すものであった。
また鶴には他の特質も与えられた。例えば賢者としての性質、または精神の気高さ(おそらく、鶴が空のとても高いところ、しばしば4千メートルにもなるところを飛ぶからであろう)、優美さ(ゆったりして高貴な動き、その四肢のすらっとした長さから生まれてきたイメージであろう。特にオオヅルは5メートルに達する時もある)、雄々しい健気さ(1644年、満州地方からの侵略に対してできるかぎりの抵抗をしようと試みて、その国のある尼僧、方七娘は新たな拳法を編み出し、それに「白鶴拳」という名前を与えた)、などといった。
そして、ついに紙に戻ってきた。最後の、そしてドラマティックな曲がり角の時間だ。
ササキサダコは1943年の1月7日に、広島のある街で生まれた。つまり、1945年8月6日午前8時15分、あの爆弾が爆発した時には、彼女は2歳半だったわけだ。サダコは爆心地から2キロメートルのところに家族といた。彼女の家のそばのすべての家が崩壊しているのを、また隣人たちがみな死んでしまったか深く傷を負っているのを、そして彼女自身はどこからも血を流しておらず、どこにも負傷はなく、手足を動かすことができることを見て取って、彼女は自分が生き残ったのが極めて運が良かったのだと一人つぶやいた。
十分体が大きかったので、彼女は歩いていくことにした。
自分が十分に元気だと示すために。そう示すことは、おそらくまた、できる限り早くその場から離れるために必要なことであったのだ。
1954年、競争の途中で、彼女はめまいに襲われる。白血病の診断がくだされた。
誰か、一番の親友だと言われている人間が、彼女に千羽鶴の話をした。
その古い伝説に従えば、折り紙によって千羽の鶴を組み立てたものは、その願いが聞き入れられるというのだ。
「私は、治りたいわ」とサダコは言った。
そうして彼女はその鶴に手をつけた。
彼女は折り始めた。朝から晩まで、彼女は折った。彼女は自分の見つけた紙はすべて折った。トイレのちり紙に至るまで、処方箋、薬のラベルに至るまで。
そして夜になっても、彼女は続けた。眠ることを受け入れないならば彼女を縛り上げると看護師が脅さなくてはならなかったほどだった。そうして彼女の部屋は鶴で満たされていった。
彼女の折った鶴が500羽に達した時、少し調子が良くなったように感じられた。彼女は伝説が成し遂げられているのだと信じた。彼女は家に帰ることが許された。が、小康状態は一週間しか続かなかった。
その後もまだ、彼女が144羽の鶴を作る時間は続いた。そして、1955年の8月25日、彼女は亡くなった。
彼女は12歳だった。
彼女のクラスメイトたちは、彼女のために紙の鶴を折り続けた。
鶴は1000羽にすぐ到達した。そしてそれを越えて続いていった。クラスメイトたちは自分たちのある考えを持っていたのだ。その鶴をすべて売った売上で、広島の真ん中に、爆弾にやられ、即座に、あるいはサダコのように時間をかけて死んでいった子供たちに捧げられた像が立てられた。儀式は続けられた。毎年、宗教にかかわらず、世界中の無数の学校から、何千何万もの鶴の折り紙の山が届けられている。
その精神性のもっとも深い部分において、ササキサダコは、あの中国の尼僧、白鶴拳を編み出した、方七娘の妹なのだ。
(訳者注)ここまでの文章を見ると、明らかに富士山と海の間を抜けて関西に向かっているように思われるのだが…。地理的になにがどうなっているのかよくわからない。
(訳注)「井川意高」氏、であろう。おそらく、「井川前会長」という報道を見て、「井川前」「会長」と思ったのだろう。面白かったので残した。
|