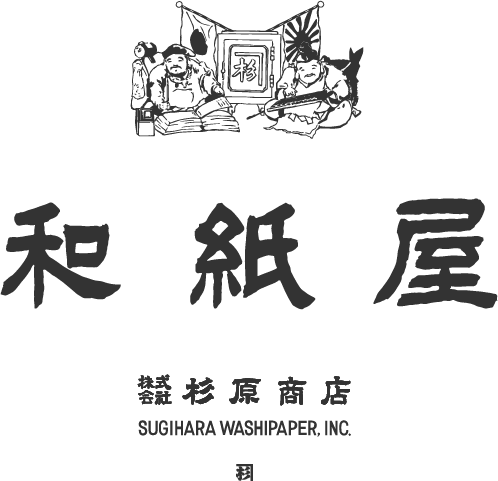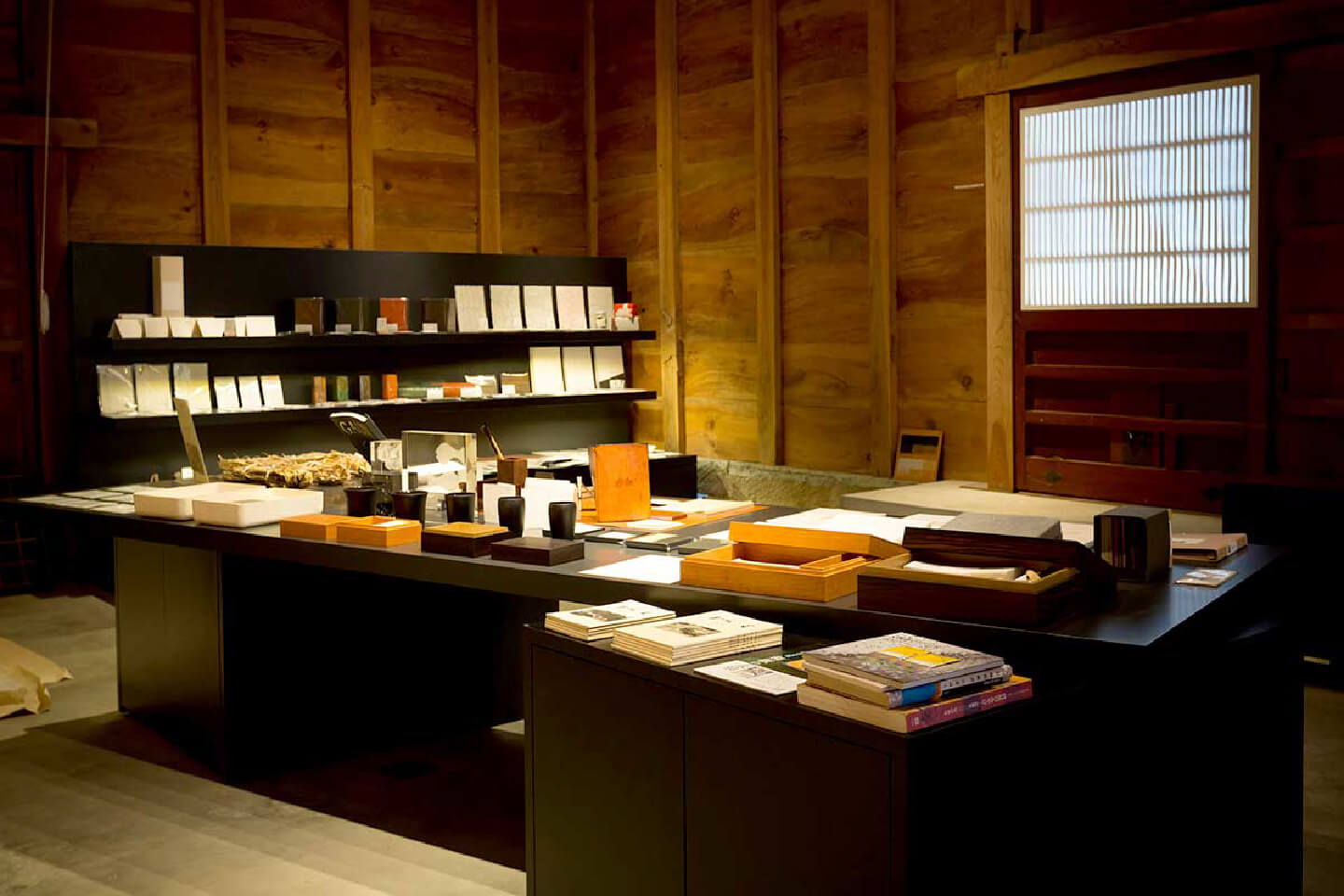WASHIYA SUGIHARA WASHIPAPER, INC.
17-2, oizucho, echizen-shi, fukui
website / 和紙情報はこちら
Architect and Prescriptor and Interior designer /
建築家様やデザイナー様に向けて、
OPEN TUE-FRI / 9:00-13:00
4TH SAT / 9:00-12:00 / 14:00-17:00
★完全予約制とさせていただきます★
0778-42-0032
sugihara@washiya.com